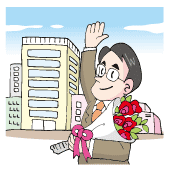引き続き健康保険に加入したい
- 退職後の健康保険にはいくつかの選択肢があります。それぞれを比べると保険料や給付内容など違う点がいくつか出てきます。どの保険に加入するかはご自身の判断になります。よく検討して一番適切な制度へ手続きをしましょう。
任意継続に加入する
退職後も在職中と同様、テルモ健康保険組合の被保険者および被扶養者の資格を継続できる制度です。医療費の自己負担額軽減(付加給付)・健康診断(人間ドック等)・各種補助制度など同じ条件で 受けられます。
| 加入資格 | 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者資格があった人 |
|---|---|
| 保険料 |
前納制度により保険料を一括前払いすることも出来ます。(※毎年3月、9月にご案内します) |
| 加入期間 | 退職日の翌日から2年間 |
| 保険給付 その他適用制度 |
|
| 手続き期限 | 資格喪失後20日以内に保険料納付 |
| 給付金の振込 |
|
家族の被扶養者になる
退職後、家族の収入で生活する人は家族の被扶養者になるのも選択のひとつです。
被扶養者になれるかどうかはその健康保険組合の認定基準により決まりますので、家族の健康保険若しくは勤務先にお問合せください。
| 加入資格 |
|
|---|---|
| 保険料 |
|
| 加入期間 |
|
| 保険給付 その他適用制度 |
|
| 問合せ先 |
|
国民健康保険に加入する
わが国は国民皆保険制度で、国民だれもが医療保険に加入することになっています。職場の健康保険、国保組合(同業者等で組織する)、任意継続被保険者制度に加入していない人は国民健康保険の加入者(被保険者)になります。被扶養者という資格はなく家族全員が被保険者となり、保険料は市区町村により異なります。
国民健康保険の詳しい内容についてはお住まいの市区町村にお問合せください。
| 加入資格 |
|
|---|---|
| 保険料 |
|
| 加入期間 |
|
| 保険給付 その他適用制度 |
|
| 必要書類 |
|
| 問合せ先 |
|
再就職先の健康保険に加入する
再就職先したら、再就職先から保険証をもらいましょう。
保険証表面の資格取得日が保険証の発効日です。
| 関連ページ |
|---|